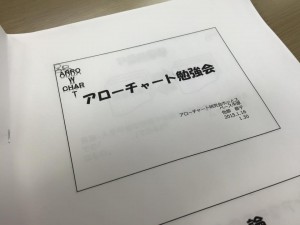ある福祉バカが目から落としたウロコ
昔々(といっても10年くらい前)、山口県に自他共に認める福祉バカがいました。
この福祉バカは、福祉のことが大好き過ぎて、他分野の学問的業績を認めないばかりか、半ば見下していました。
やがて縁があり想定外の転職をすることとなり、(こともあろうに特に)見下していた文学を礎とする大学の教員になってしまいました。
福祉バカは考えました。「文学なんて実社会では何の役にも立たない。まぁ、縁があって就職したのだからホドホドにやっていこう」と。
そんなある日、福祉バカは学食で偶然学長と隣り合わせ、一緒に昼飯を食べることになりました。
一兵卒の福祉バカが学長と並び食事を共にすることなどなかなかありません。 年を重ねても恐れを知らぬ福祉バカは、チャンスだと思い、こう訊ねました。
「学長! 文学を学んで何の役にたつのでしょう? そもそも、文学は何を究める学問なんですか?」
学長はにこやかに、そして間髪を入れずこう言いました。
「文学は、人間理解ですよ。」
僕の箸は止まりました。
同時に、食べかけの天ぷらうどんの中に、音を立ててウロコが落ちていきました、目から。
「じゃあ、僕がやって来たことと同じなんですね?!」
静かな学食に福祉バカの声が響き渡りました。
学長は、福祉バカの問いに答える代わりに、
「文学の主人公は、たいていマイノリティですよね。昔々或るところに働き盛りの若い夫婦がいました、なんて始まる話なんてあまり聞きませんよね。」そう続けました。
ここから福祉バカの【他者理解】の模索は始まったのだと思います。
もしかしたら、福祉バカが(恐れ多くも)教員の道をも歩み始めた瞬間だったのかもしれません。